電力需要は電化で増加へ 供給力と投資環境整備が課題に(Enelog62 VOICE)
Summary
TLDRこのスクリプトは、電力需要の将来のトレンドと、省エネ効果による影響について述べています。2030年までに電力需要が減少する傾向があり、その後は再び増える可能性があることが示されています。また、EVの普及により電荷が増加すると見込まれ、産業分野でも技術の進歩により電荷が上がる可能性があると述べられています。さらに、海外でのビジネス機会や日本の電力技術の輸出、新設ビジネスの機会の増加などが触れられています。最後に、電力供給力の確保と、水素やアンモニアの導入、エネルギー安全保障の観点からの国産水素の確保など、日本のエネルギー政策の今後の課題が議論されています。
Takeaways
- 🔌 電力需要の予想:2030年には2兆W程度の電力需要が見込まれ、その後も徐々に増え続ける可能性がある。
- 🚗 EV(電気自動車)の普及:EVの常用化が進むことで、電力需要が増加すると見込まれ、50%程度の増加が期待されている。
- 🏭 産業分野の電力需要:現在は見通しが難しいが、30%程度の電力需要が増加する可能性がある。技術の進歩によりさらに増える可能性も。
- 🌐 海外ビジネスの機会:日本の電力業界が海外で新設ビジネスの機会を探すことができると見込まれる。
- 🔋 電力システムの品質:日本の高品質な電力システム制御技術が海外に展開されることが期待されている。
- 🌿 環境に優しいエネルギーの導入:日本は石炭やLNGの輸入国であり、将来的には水素やアンモニアの導入を進める可能性がある。
- 💡 電力需要の増加と電源体制:電力需要が増加すると、現状の電源体制では供給力の確保が課題となる。
- 🌬 再生可能エネルギーの問題:太陽光や風力発電の増加による夕方のダークカーブ問題や、安定した風力がない地域の課題。
- 🏗️ 設備の維持と更新:老朽化する発電所の対策が重要であり、既存の要子を守る戦略が求められる。
- 💸 投資回収の課題:新設設備の投資回収が難しい状況下、事業者に対する固定費回収の制度が提案されている。
- 📈 民間事業者の役割:民間事業者が投資を進め、事業利益率を確保する体制を築くことが国のエネルギー政策にとって重要である。
Q & A
電力需要の将来の見通しについてどう思われますか?
-2030年までにやや減少する見通しですが、その後は再び伸びることが予想されています。
EVの普及がbringingどの影響を与えると思われますか?
-EVの普及により、電荷率が約50%増加すると見込まれています。
産業分野で電気の利用にどのような見通しがありますか?
-現在は電荷がどの程度進むかの見通しが難しいとされており、現在の電荷率は約30%程度です。
日本の電力業界が今後どのようなビジネスチャンスがあると思いますか?
-海外での新設ビジネスの機会が増えるため、日本の電力業界は海外でのビジネス展開に期待できます。
日本の電力供給力の確保についてどう考えていますか?
-供給力の確保は重要であり、特に水素やアンモニアの導入を支援することで、アジア諸国への影響力を強化することが求められます。
日本の電力会社が直面している課題は何ですか?
-太陽光や風力発電の増加による夕方のダークカーブ問題や、老朽化する発電所の対策など、多くの課題があります。
日本の電力供給体制についてどう考えていますか?
-現行の供給体制では電力不足が生じる可能性があり、最後の頼りになる電源が重要となります。
日本のエネルギー自給率についてどう思われますか?
-エネルギー自給率の問題は重要であり、サネの増加に伴い、自給率の向上が期待されています。
新設電源の投資回収性についてどう考えていますか?
-投資回収性は難しい状況にあるものの、国が長期ダス炭素電源のオークション制度を導入することで、固定費回収が期待されます。
民間事業者が電力市場で活動を続けるために必要なことは何ですか?
-一定の事業利益率が確保できる体制を作り、株主や投資家に対して説明責任を果たすことが重要です。
日本の電力政策の将来展望についてどう思われますか?
-電力政策の将来展望は、省エネルギーや電力需要の増加に対処するための戦略が求められるでしょう。
Outlines
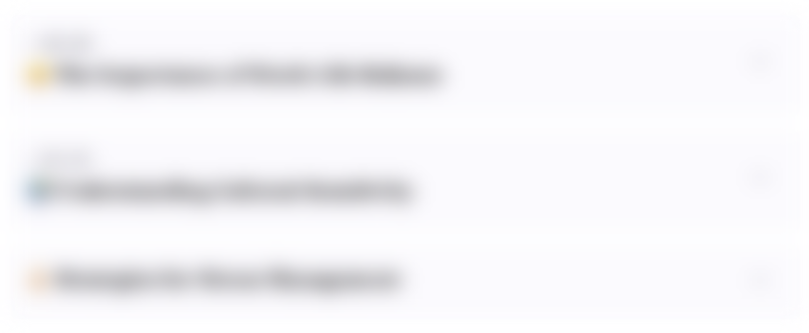
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowMindmap

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowKeywords

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowHighlights
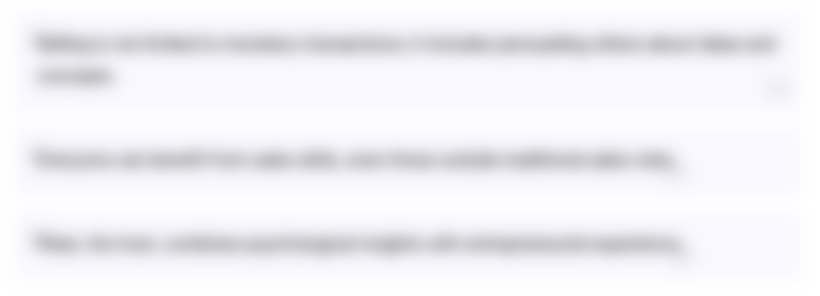
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade NowTranscripts
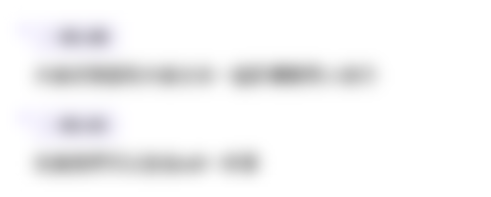
This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.
Upgrade Now5.0 / 5 (0 votes)






